|
|
|
丘のうえの小さな写真館 北国通信の世界
|
|
|
|
第111号 北国通信『プラナーレンズとの出会い』 2005年10月
|
|
|
|
 |
|
|
|
レンズ構成5群7枚 |
|
|
|
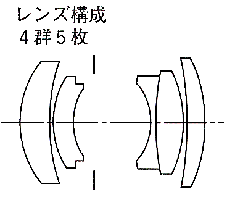 |
|
|
|
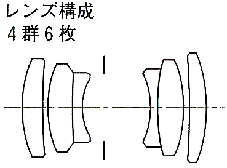 |
|
|
|
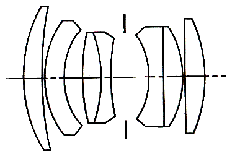 |
|
|
|
マクロプラナー120mmf4
|
|
|
|
プラナー80mmf2.8
|
|
プラナー100mmf3.5
|
|
|
|
●NO1
カレンダーを制作などが長引いて撮影ができなくなり、身動きがとれなくなると、決まって撮影機材の見直しをする。このことは、僕が18年間続けているリズムとも言える。
しかし、その撮影機材にはお金が伴うから、このことは健康的なリズムとは言えない。しかし、自分が考えるどんな状況に対しても理論的に必要だと思うレンズを考え、揃えていこうとすることは大事なことだ。
こう言ってしまえば、簡単なことに聞こえるのだが、高価なレンズのことゆえ、そう簡単にはいかない。
そしていつの日か、少しはゆとりを感じさせるようなレンズも購入したいと思うのだけれども、いまだにそんな余裕は経験したことがない。いつも、必要なものを順番に揃えて行くだけで精一杯だった。
そして数年前までマミヤM645というカメラを10年少し使い、皮肉なことに長年揃えられずにいたレンズ群をようやく全部揃え終わった矢先、撮影機材をハッセルに変えることになる。今度は一からハッセルのレンズを揃えていくことになる。丁度今から3年前の12月頃のことである。
3年前の12月、念願だったハッセルブラッド一式を購入。あれから3年、ハッセル用のレンズは定価にすると1本30万円を下回るレンズはなく、それをまずは少なくとも6本は揃えなくてはならなかった。 またしても苦しいレンズを揃えていく生活が始まる。
こうして、3年後の今、魚眼レンズのフィッシュアイ・ディスタゴン30mmF3.5とディスタゴン40mmF4を除く 13本のレンズを揃えるに至る。
ハッセルブラッドはスウエーデン製のカメラだけれど、このハッセルに供給されるのはドイツのカール・ツアイス社・Carl Zeiss社のレンズで、ツアイスのレンズは広角レンズをディスタゴン、標準をプラナー、望遠レンズをゾナー、超望遠レンズをテッサーとしている。(厳密にはレンズ名称はレンズ構成の違いによる)
その中で、今回お話ししたいのが、標準レンズのプラナーのこと。
標準レンズとは人間の目の見える範囲が視野47°前後なので、それに近い画角のレンズのことを標準レンズと呼んでいる。
プラナーとはドイツ語で“平坦”を意味する言葉で、1897年にアッベ博士の助手を務めたこともある ツアイスのパウル・ルドルフ博士が作った。
|
|
|
| ●NO2
フィルムは小さくても対角線で50mm、大きければ90mmもの大きさがあるから、レンズはそんな大きな円上の全ての点で均一な画質を得なければならない。こうしたところに、レンズ設計の難しさがあり、色々違った形や材質のレンズを組み合わせて、最良の組み合わせを考えていく。
昔は、コンピューターがなく、全て手計算でレンズ設計をやっていたという。そしてレンズ設計には膨大な計算が伴ったために、社内の女性社員がかり出されて、ひたすら毎日毎日計算をさせられたのだという。
こうして、血の出るような計算の末に生み出されて来たレンズの一つがこのプラナーレンズであり、当初はゾナーなどよりも劣るとされていた。しかし、コーティングというレンズの表面反射を除去する方法をアレクサンダー・スマクラ博士が開発して以来、プラナーなどのダブルガウスタイプのレンズ形式が再評価されるに至ったのである。
こうして、プラナーは現在に至るまでツアイスという世界最大のレンズメーカーの看板レンズとして君臨することになる。
こうしたレンズの歴史を見ていくと、果樹づくりに似ていることがあるのに気づく。
今私たちがうまいうまいと食べている果樹はその全てが何万という品種から選ばれた超超優等生で、リンゴなら、フジの方が…とか、いや、つがるの方が…などと言っているのに似ている。
果樹は数万の苗木からの選抜し、プラナーなど現代に残っているレンズは無限のレンズの組み合わせの可能性の果てに残った、超超最高のレンズの組み合わせだと言える。しかしどちらも面白いのは、いくら計算的にすばらしい果樹やレンズであっても、それだけでは生き残っていけないということだろう。
果樹もレンズも最後は人間の“感覚”が判断するからだ。これまた選りすぐりの人間の感覚に支持された果樹やレンズだけが生き残っていく。優秀であることの上に、更に人間の感覚の厳しいハードルを越えて初めて、時空を越えて広く人々に愛されるようになる。本当に気の遠くなるようなことである。
さて、このプラナーをどうしてここで紹介したかったか。
実は、最近になってようやく自分はプラナーの写りが好きだということに気がついた。ようやくわかったとも言えるからだ。
カレンダーの制作で撮影しない日々、プリントを冷蔵庫の味気ない壁に貼って眺めるのが僕の習慣の一つになっている。そんな日々、プリントを眺めて、そのすばらしい仕上がりを何気なく見て過ごしていた。 そしてそのたびに僕は「このシャープな中に含まれる濡れたような表情が好きだなあ〜」と思うようになった。しかし、6×6判の6cm四方のフィルムからでは10×にも伸ばせば、この濡れたような質感はきっと失われるに違いないから、どうしてももっと大きなフィルムで撮影しないといけないなあ、とそんなことばかり考えていた。
しかし、慶ちゃんがあるとき一冊のハッセルのことが書かれた雑誌をプレゼントしてくれて、その雑誌を何気なく読んでいた。その時、プラナーの記事が目に留まり、それでどうして自分が冷蔵庫に貼って眺めていた写真の品質が気に入っていたかがわかった。
その雑誌の記事には次のようなことが書かれていた。「プラナーを褒める写真家は多い。代表的なのは鮮鋭なのに描写はソフトだという意見だ。…」とあった。この一文を読んだとき、僕はこれだと思った。 僕が冷蔵庫に貼った一枚のプリントの写りがすばらしいと感じていたのは、このことだと確信したのです。つまり、鮮鋭な写りなのに、柔らかさがある。この一見矛盾する描写こそ、プラナーの魔法なのだと思った。
|
|
|
|
●NO3
一眼レフライカのズミクロン50mm f2というレンズや慶ちゃんの持っているエルマー50mmやM型の近接ズミクロンなども確かに滲みはあるのだけれど、それは反逆光か逆光などの条件の時だけで、太陽を背にした順光の撮影条件では、幾分乾燥気味な写りをするようになる。しかし、ツアイスのプラナーはどんな絞り値でも、どんな光線状態でもいつも鮮鋭な中に滲みのある写りをする。こんなところに、ライカとツアイスの違いを感じる。そして、これと同時に自分がどんなにこのプラナーの写りが好きだったのかもわかった。 先月お送りした草葉の作品も実はこのプラナーの中の代表であるプラナー80mmF2.8というレンズで写したものです。どうですか、逆光でもないのに、どことなく濡れたような感じがしませんか?この滲んだような感じこそプラナーの写りのようです。
国産のマミヤやニコンなどではどうしてもこうした写りはしなかったので、いつも僕は滲みを造り出すフィルターを使いましたし、今もよく使っています。しかしこのフィルターを使うとコントラストが落ち、対象の輪郭がぼけたり、ハイライトが必要以上に飛び気味になるなど、克服できない問題をはらんでいました。従って、フィルターによる、滲んだ作品の創出にはふさわしくない状況があり、もっとコントラストを維持しつつ、滲んでほしい状況と無数に出会っていたのです。そんな折り、マミヤをやめ、僕は何かに導かれるようにハッセルに向かい、プラナーの描写に出会うことになります。
しかし、その今でもフィルターにより、自分の好みの画に仕上げていくことも僕はとても大切なことだと思っていますので、今後更にフィルターを研究して、自分がこうだとする写りを模索していく努力を続けていこうと思っています。
そこで、今回は、季節的には180°かけ離れるのですが、このメップ岳に続く道の作品を見ていただきたいと思います。
この作品は、今年の春に写した道南のメップ岳での作品で、プラナー100mmF3.5に滲みを付けるソフトフィルターを加えて写しています。そのことにより、滲みは強調されて、雰囲気のある作品に仕上がり、心に残る一枚になりました。いかがでしょうか。
さて、この作品を選んだ理由としてもう一つ、ハッセルブラッドの可能性のことをお話ししたいと思います。何度か6×6判から10×近く、すなわち60cm四方に伸ばしてみると、粒子の荒れが目立ち、これではせっかくの鮮鋭度やソフトな感じが失われるだろう、ということを僕はずっと気に病んでいました。それで、どうしても6×6判以上のカメラを使わなければ、全紙において、品質が維持できないと考えていました。しかし、実際に4×5判という10cm×12.5cm程のフィルムを使うカメラでは、理論的に6×6判並のレベルのものしか作れず、品質を高めるためにはそれ以上の大型カメラを使わなければ意味がない、と慶ちゃんと二人結論に達していました。すなわち、8×10という途方もない大型カメラ(4×5判の4倍の面積のフィルムを使うカメラで20cm×25cmという巨大なフィルムを使う)でなければ、違いのわかる結果を得ることはできないだろうと考えました。
|
|
|
|
●NO4
つまり、ハッセルの6×6判を越える高い品質の写真を撮影するためには、8×10という超大型カメラを使う他に方法はないだろうという結論に達したわけです。想像さえできないと思いますが、8×10という超大型カメラはカメラだけでもゆうに5kgを越え、20cm×25cm、すなわち315mmもの広い範囲に結像できる広いイメージサークルを持つレンズを用いるため、レンズも2kgを越えるようになります。おまけに例えカメラやレンズを揃えることはできても、引き伸ばし機(ネガから印画紙にプリントする機械)を揃えることが難しい、との判断から8×10を使うことには無理があると判断しました。
今までお話ししてきたように、確かに8×10といった超大型カメラを使うと、プリントの品質は最高域に達するわけですが、何もかもが大がかりになり、ここぞといったときに使えなかったり、フィルムの価格も高くて枚数が買えなかったり、現像に時間がかかりすぎたりと、問題を多く抱えることになってしまうのです。
その反面、6×6判は微粒子のフィルムをきちんとした現像をすれば、4×5判と互角かそれ以上の品質に仕上げることも可能で、しかも、フィルム代は4×5判の1/5にとどまり、現像時間は一度に50枚以上の現像ができるために非常に効率がよいのが大きな特徴だと言えます。なかでも、フィルムの値段が1/5ということは撮影時に何枚もレンズを変えて写したり、フィルターを入れたり入れなかったりと、たくさんの可能性を探っていけるという、初心者にはもってこいというわけです。
こうして、今回の作品もハッセルならではのフィルムの値段が安いということを良いことに、フィルターを入れたり入れなかったりと十数枚写した中からプリントしたというわけです。こうした手軽に撮影できることから生み出されてくる予期もできなかった美しいプリントを得られることに、ハッセルなど6×6判の大きなメリットを感じたということです。
そういうわけで、6×6判からこれ以上大きなプリントにすれば、確かにアラが目立ってくるとは思いますが、このくらいではびくともしない力を持ちつつ、大きな可能性を持たせてくれる6×6判はすばらしいような気がします。ただし、フィルムが小さいですから、撮影時のぶれやぼけは絶対に禁物で、引き伸ばしの時のレンズやコンデンサーレンズの果てに至るまで最高の品質を貫かなくてはならないだろうと思います。
撮影時のぶれのことですが、十分な三脚を使った上で、レリーズを使い、息を止めて慎重に撮影しても、撮影時のぶれを完全には止めることはできません。こうした撮影時のぶれのほとんどが、シャッターを押す瞬間のもので、このシャッターを押すときにどれだけ余計な力を加えずにシャッターを切れるかが、鍵になります。もっとも、このことには限界があり、現実の状況と照らし合わせてやるほかないのが実際だと思います。
また、これ以上画質を追求せずに、6×6判にとどまる決心を付けた理由に、今後の撮影が地元にとどまるものよりも、旅を主体にした撮影に変えたいという思いがありました。そうすると、確かに画質的には大型カメラには劣るのですが、その分、フットワークが軽くなったり、撮影に費やす時間が軽減されるメリットが生まれてくると考えたのでした。
しかし、自分が尊敬する前田真三先生やアンセルアダムスなどは大型カメラを駆使して、実に緻密で繊細な作品を旅の途中で作られており、僕もそうありたいと考えていたのです。
しかし、僕は前田真三先生やアンセルアダムスのような一枚の大作づくりをしてみたいわけではなく、写真を複数枚によって一つの世界を構成するものと考え、数多く撮影した作品を組み合わせて、写真作品の枠を越えた何かを表現したいと考えています。つまり、写真作品の大作を作り上げるのではなくて、写真作品を組み合わせて作り上げてできる別の作品を作ろうと思っています。こうした手法の方が今の自分には似合っていると思いますし、そうした結論を支持してくれたのがプラナーの写りであったわけです。
|
|
|
|
●NO5
2006年カレンダーの制作終盤戦
11月3日現在、2006年カレンダー&2006年ポストカードの制作はようやく終盤戦を迎え、ポストカード、カレンダー共に、ようやく校了です。
長い長い道のりでした。過ぎゆく秋の気配を横目で見ながら、僕たちはカレンダーを作り続けました。 そして、僕の真剣な姿勢に製版会社の技師も印刷会社の技師も皆、しっかりと答えてくれて、最高の技術を見せてくれました。
写真の印刷では、まずスキャナという装置でフィルムをデジタルのデータに変換して、それをコンピューター上で色を調整し、できあがったらそれを紙に印刷します。
こうした一見簡単なことでさえも、現実には難しい問題が介在しています。たとえば、スキャナと呼ばれる機械はシステム全体で1億円ほどします。家庭によくあるスキャナは今では数千円ですから、同じスキャナでも値段の差は驚くほど違います。ちなみに、僕が使っているスキャナはドイツのハイデルベルグ社の60万円ほどもするものですが、これでもポストカード1枚作ることができません。1億円のスキャナに対して、濃度レンジと呼ばれる読み込める色の範囲と諧調が違うのです。
こうした、スキャナの値段の高さは大きな障害となり、自分が持つことはできませんからどんな作品に仕上げたいかを、スキャナの技師に一生懸命伝えて行かなくてはいけません。だからポストカードやカレンダーを作っていくということは、どんな仕上げをしたいかという自分の意志をどれだけ製版技師に正確に伝えられるかが勝負で、また、どれだけ製版技師が僕たちの気持ちを汲んでくれるかにかかっていると言えます。
こうした、製版会社、印刷会社との絶妙な連携がなければ品質の高いポストカードやカレンダーはできないのです。何でも一人ではできないと、痛切に感じる時です。
こうして、今回のポストカードもカレンダーも最高の品質が保証できるところまで、仕上げることができました。もうちょっとでカレンダー&ポストカードできましたの案内状が届くと思いますが、是非ご覧下さい。
特に、今年はカレンダー&ポストカード完成のカタログも印刷機で印刷してもらったので、とても綺麗なのが行くと思います。今まで、丘のうえの小さな写真館内のインクジェットプリンター6台をフル稼動させて、まる一週間寝ずの戦いの末に造っていたものですが、今年から印刷していただくことにしましたのできっと見やすいと思います。
その他、2006年カレンダーでは2月、3月、4月、5月と年間カレンダーの2作品はハッセルブラッドによる作品です。特に、3月、4月、5月はいずれも世界一の超広角レンズと呼ばれるハッセルのビオゴン38mmF4.5によるものです。こうした超広角の世界は今までマミヤ時代にどうしても撮ることができなかったので、この領域の写真をこうしてカレンダーに生かしていけることはとても嬉しいことです。もちろん、カレンダーサイズに合わせて上下をトリミングしていますので、実際はもっと上下が入っています。
また、ポストカードでは日本列島縦断の旅からの4作品を含み、日本の作品を6枚。北海道の作品を10枚作りました。この日本の作品6枚は今後、日本的な和の情感を感じるポストカードを増やしていきたいという思いの先駆けとなり、気に入ってもらえるかどうか、とても心配なところです。もし、この和の情感がある程度気に入っていただけるようであれば、次なる目標としてヨーロッパなど「洋の情感」を感じる作品を作っていくことです。その意味でも、今回新たに作った日本の和の情感のポストカードはこれからの僕らの航路を占う大切な大切な6枚になります。でも、やるだけやったので、後は神様に祈るほかないです。
|
|
|
こうしてカレンダーやポストカードはほぼ完成したのですが、その代わりこの夏から秋はとうとうどこにも出かけられないで過ぎていきました。心の中にはたくさんのたくさんの秋の撮影のことを考えていたのですが身体は二つありませんから仕方のないことです。しかし、そうした中で、これ以上単なる画質の品質を高めることはせずに、今のところはハッセルまでの撮影にとどめ、そうしたことで生まれるゆとりの中から、他の可能性を探っていこうという、大事な結論を導きました。
僕の場合、それが多すぎますが、人生、止まってよく考えることも大事なことです。
そういうわけで、以下に過ぎゆく秋を偲んで、丘のうえの小さな写真館の庭の小さな秋のお散歩につき合って下さい。 |
|
|
|
 |
|
|
|
秋も過ぎゆく頃、荒れた庭の所々でバラが咲きます。手入れの状態は悪いので、生き残ったバラはどれも 強健なバラばかり。それでも、紅葉した樹木の葉とバラの組み合わせは美しいものです! |
|
|
|
 |
|
|
| ムラサキシキブの実。9月から10月頃花を咲かせ、その後すぐにこうした実を結びます。数年前どうしてもほしくてどこかで買ってきたものが、ものすごく大きく立派になりました。 |
|
|
|
 |
|
|
|
やはり素人果樹栽培はブドウ!特に気候に適したキャンベルアーリーは良いだろうと思い、一昨年から館の西壁で栽培開始。今年初めて少しは食べられそうな実が実りました。 |
|
|
|
 |
|
|
コンクリート基礎の味気なさが嫌で、数年前から蔦を植えるようにしましたら、150円で買ってきた蔦がとても美しくなりました。白い柵と絶妙です。 |
|
|
|
 |
|
|
|
これはアジサイの花が咲き終わって、茎についたままドライフラワーになった状態。玄関のところにあるのですが、毎日見ても飽きない美しさです。 |
|
|
 |
|
|
|
今度はガクアジサイのドライフラワー状態の花。これも絶妙。
|
|
|
 |
|
|
|
カシワバアジサイの大きな見事な葉の紅葉。
|
|
|
この他にも、ブナの紅葉やホワイトリーフポプラや、ナナカマドの紅葉や白樺の黄葉なども綺麗ですし、3種あるカエデの紅葉も実に綺麗です。カエデは特に好きなのですが、カエデの木に合うほど庭は広くないのでとても残念です。もし土地があったら、そこに好きな木をずらっと並べてみたいものです。夢ですね!
もうすぐ本州も紅葉ですね。紅葉鑑賞はお考えですか?僕らは紅葉鑑賞に行けませんでしたが、どうか僕らに代わって紅葉の鮮やかさ、しっかりと目に焼き付けてきて下さいね!!よろしくお願いします。 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|